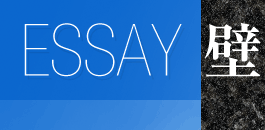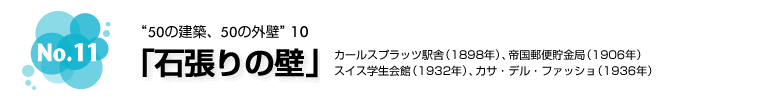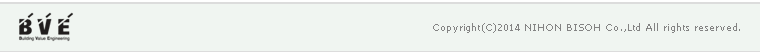|
大雑把な話をすれば、石は近代建築の発展とともに、外壁から排除されていった素材の代表である。組積造という石壁に依拠した構造からの解放があり、外壁が床や屋根を支えるものから空間を包むものへと、その役目を大きく転換させたからである。つまりカーテンウォール外壁の登場だ。だが、どっこい石は生き残った。ガラスの外壁が隆盛を極める今日でも、豪華さや重厚さといった、永遠なる素材である石にしか求め得ない意味をファサードに与える場合、石は形を変えて積極的に使われる。
現代の建築外壁に登場する石のほとんどすべては、板状の石である。その厚さは5〜10mmが多く、石タイルと呼んだ方が適しているか。それを目地幅10mm程度で張って外壁の仕上げとするのが、現代である。
積むことから張ることへの転換。この板石としての使用にいち早く思い至り外観表現に活用しようと考えた建築家が、ウィーンのオットー・ワーグナーである。彼はオーストリアがまだヨーロッパ最大の帝国であった時代の人だ。だからその考え方の根底には、ハプスブルク王朝の華麗な石造建築群の伝統を、20世紀でも守ろうという意識があっただろう。ともかくも彼は、石積み石造ではなく、<板石張り石造風>の外観を生み出した、その輝かしい先駆者となった。
例えば、19世紀末の代表作であるカールスプラッツ駅舎(1898年)では、厚20mmの白大理石板で外壁が構成された。構造の鉄骨柱間にはめ込んで組み立てた、プレファブ工法の最初期の例でもある。板石への装飾は、金彩
でヒマワリをプリントする程度にとどめられ、工法の合理性をその板石外装に求めていたことがわかる。ただしワーグナーのデザインに手ぬ
かりはない。大理石の下半分の表面を粗くはつってあり、この清楚な美しさの石材が被るであろう汚れを、目立たなくさせる工夫だ。
彼は板石の使用を、工法の合理化と工期の短縮の他に、経費の軽減の観点からも考えていた。つまり純粋白大理石積みの数分の一の費用で、同様の表現性を外壁に与えられるというのである。帝国郵便貯金局(1906年)は、それを明示する作品となった。
鉄骨と鉄筋コンクリートを構造に併用したその巨大なビルの外壁に、まさしく石タイルと呼ぶにふさわしい方形の白大理石板が隈なく張りめぐらされた。張り方がまたユニーク、現代のように留め金具を裏に隠すことなく堂々と見せてしまった。一枚々の石板中央の黒い点が、その固定ボルトの頭である。また大理石板はどれも表面
を薄く凸面状に湾曲させ仕上げてあり、陰影によって量感が生まれるように図られた。つまりワーグナーは、ボルトを露出させることで外壁が石張りであることを宣言する一方、その見え方という点ではかつての石造壁と同様のヴォリューム感を与え、石造建築文化の継承をはたそうとしたのだ。+
モダニズムが勝利を収めた1930年代ともなると、歴史との整合で建築家がワーグナーのように頭を悩ませる必要はなくなった。おもしろいのは、板石に備わった面
の平滑さやエッジの鋭さという特性が、モダニズムの目指す幾何学的立体という外観デザインにはもってこいであった点だ。
ル・コルビュジェのスイス学生会館(1932年)は3面を白い石張り外壁とした直方体の外観である。かつて彼はレンガの非耐力壁を塗装して白い外壁を得ていたが、それとは格段に違う平滑さと力強さを持つ壁ではあるまいか。
テッラーニのカサ・デル・ファッショ(1936年)でも白い幾何学形が外観表現の最大テーマとなり、鉄筋コンクリート構造のすべての面
が白大理石で被覆された。グリッドやコーナーや窓のエッジは、石でなくては表現しきれぬ
鋭利さをみせ、目にも鮮やかな直方体が出現した。組積造の必然として長く外壁の歴史を刻んできた石は、モダニズムの思想を明示しうる有力な外装材、板石として甦り、現代に至るのである。
|
 |
カールスプラッツ駅舎
(ウィーン) |
 |
帝国郵便貯金局
(ウィーン) |
 |
スイス学生会館
(パリ) |
 |
カサ・デル・ファッショ
(コモ/イタリア) |
|